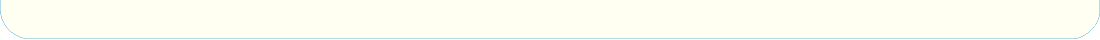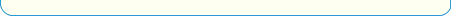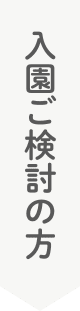すきっぷの
すきっぷの
保育へのこだわり
わたしたちが日ごろから大切にしている保育のポイントをご紹介。
「すきっぷ保育園って他の保育園と何が違うの?」というギモンにお答えします。
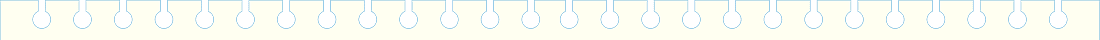
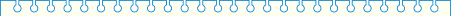
地域と手を取り合う

地域の方と共に
地域のお祭りに子どもたちが参加したり、地域の方と職員が近隣の掃除をしています。散歩では、挨拶を交わし、子どもたちが地域の中でも安心して過ごせるようにしています。
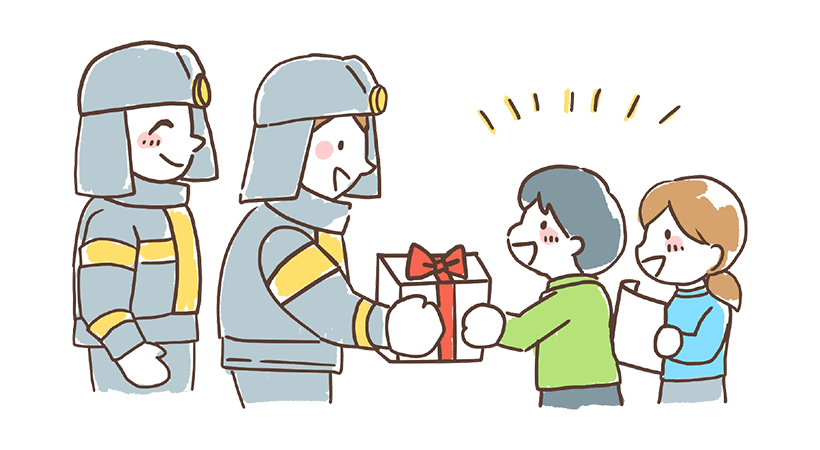
日頃お世話になっている
近隣施設へ訪問
近隣の会社や交番、消防署などに訪問し、子どもたちが創った作品をプレゼントしています。日ごろの感謝の気持ちを伝え、地域の方々と交流する場を設けています。
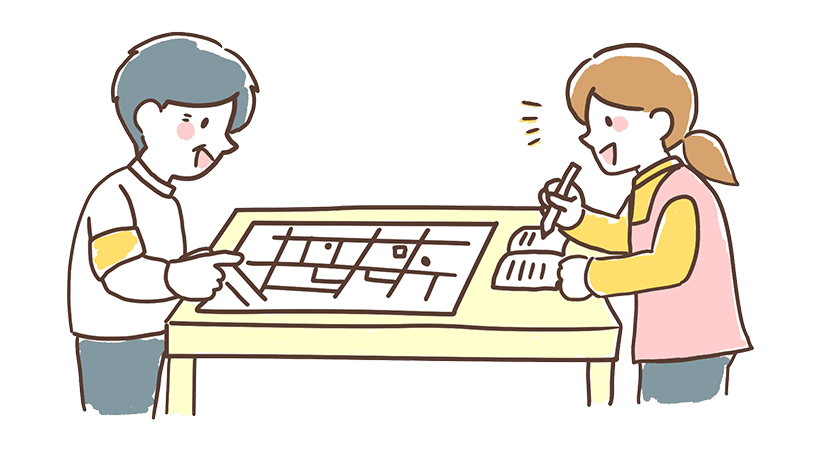
地域の安全に関する情報収集
地域の方にご協力いただいて避難訓練を実施したり、安全に関する情報共有をしながら、安心・安全な散歩コースの検討を行っています。
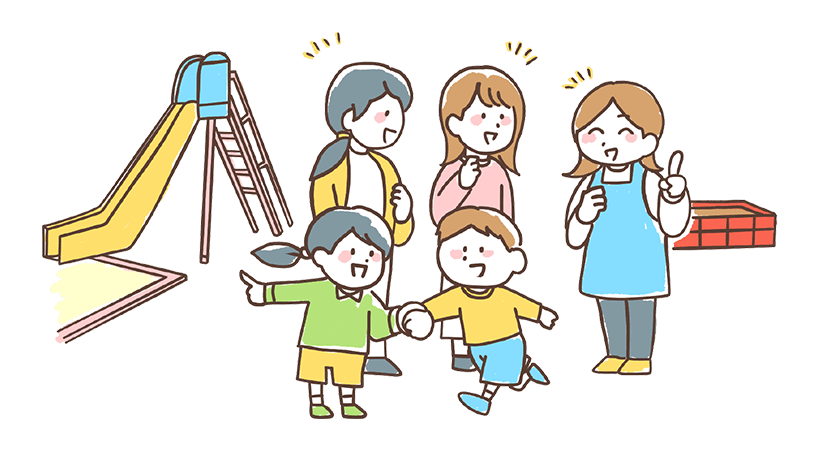
イベントを開催し園を開放
大学生によるコンサートやベビーマッサージ、運動会などのイベントに近隣の方々を招待したり、園庭開放も行っています。
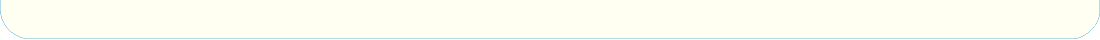
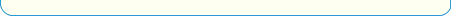
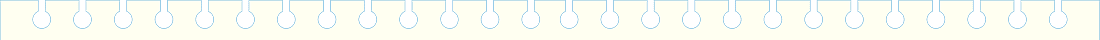
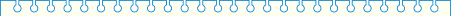
子ども一人ひとりを大切にする

遊びが満足してから次の行動へ
その子の遊びが終わりそうなタイミングをみて着替えに誘うと、「まだ〇〇したい!」と教えてくれたので、「そっか、じゃあ、〇〇がおわったら来てね。」と返事をして待っていると、遊びに満足したところで自ら着替えに来てくれました。遊びの中で子どもたちは多くのことを学んでいます。その遊びが満足できるように見守ったり、見通しを持てる声かけを大切にしています。

子どもに触れるときは
子どもの同意を得てから
抱っこするとき、鼻水をティッシュで拭くときなど、「抱っこするよ」「お鼻拭くね」とひと声添えることで見通しをもってもらい、保育者の働きかけを受けいれてもらってから子どもの体に触れるようにしています。
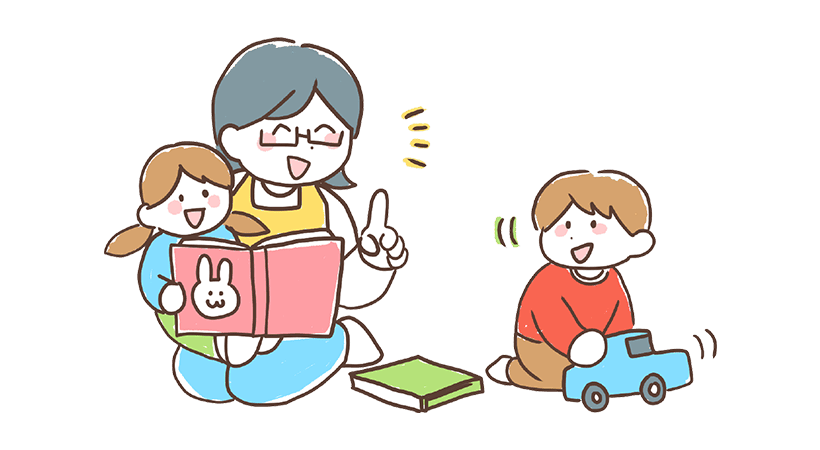
一人ひとり満たされるまで
丁寧に向き合う
子どもに絵本を読んでいると、他の子が「せんせい、よんで」と絵本を持ってきてくれました。「今〇〇ちゃんに絵本を読んでいるから、待っててくれるかな。」と伝え、終わったら、「お待たせ。待っててくれてありがとう。」と一人ひとりが満たされるように向き合うことを大切にしています。
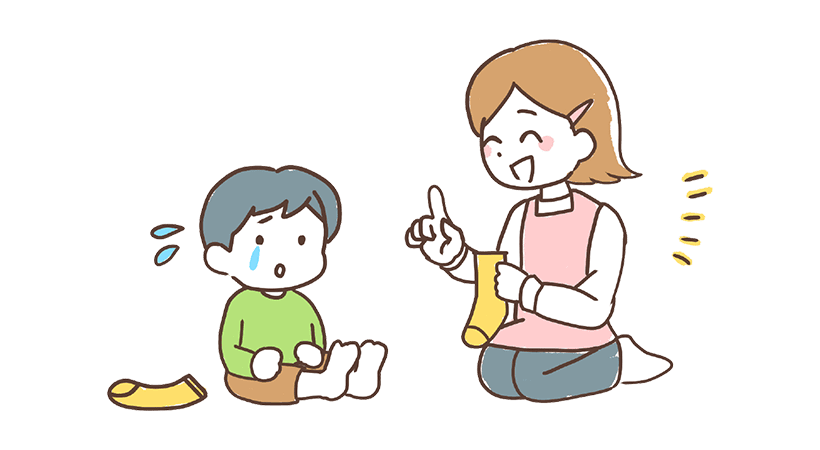
一人ひとりの"今"を
ありのまま受け止める
普段は一人で靴下を履くことができる子が、「できない!」と泣いていました。「そっか。今日はできなかったんだね。手伝っていい?」と気持ちを受け止め、履くのを手伝うなど必要な援助をしています。
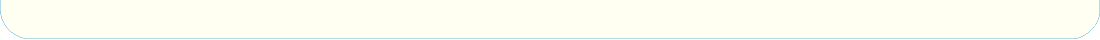
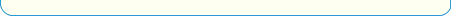
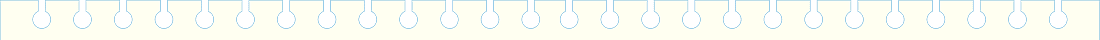
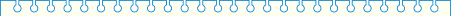
暖かな眼差しで見守る
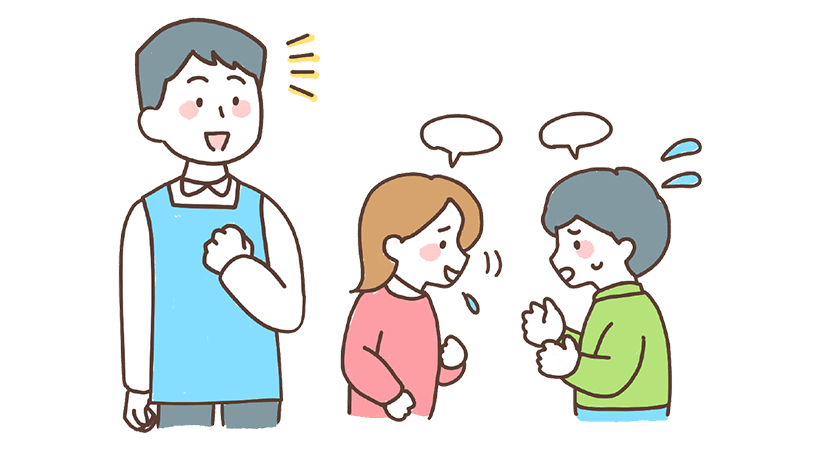
子どもたちの力を信じて見守る
子ども同士で言い合っている姿があった際、その時の様子によってはすぐに保育者が仲立ちするのではなく、フォローできる距離から見守ります。大人が解決するのではなく、子ども同士が納得できること、納得できなかった時の解決方法を見つける過程を支えることを大切にしています。

子どもの小さな"挑戦"は尊い
子どもが「やってみたい」と表現してくれたときは、できる限り見守るようにしています。思いを受け止めてもらえたこと、挑戦できたこと、成功できたこと、失敗できたこと、その経験が学びや次への意欲へつながると考えています。
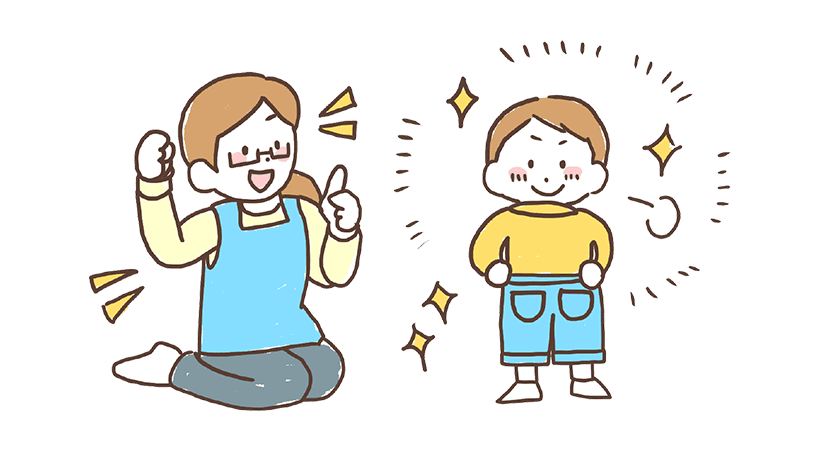
「自分でできた!」喜びに共感
子どもの「自分でやりたい!」気持ちを尊重し、うまくできなくてもその子が納得するまで見守ったり、その子に合わせてさりげなく援助をしたり、今日のその子の姿によって見守り方を考えます。「できた!」を経験できるような時間の確保、保育士の連携を大切にしています。
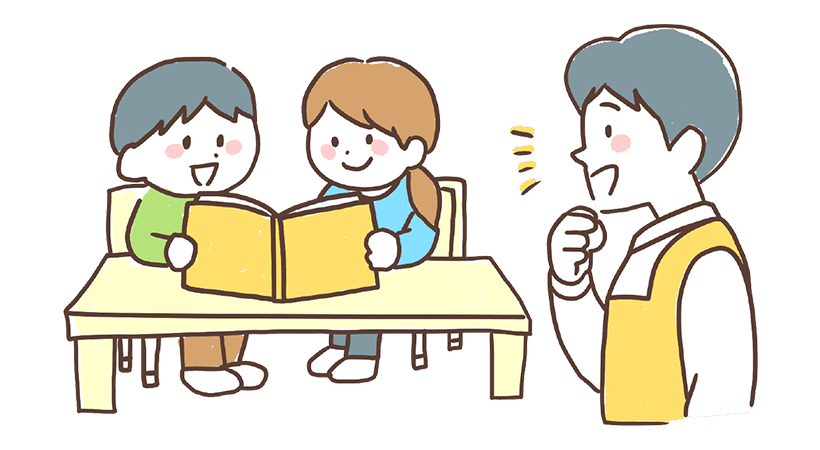
子どもの世界観を大切に
子どもたちは、大人では想像つかないところで真剣だったり、遊びだったりします。そんな世界を壊さないように、でもその世界が知りたくて、時々お邪魔しながら、子どもの世界を見守っています。
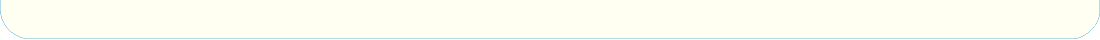
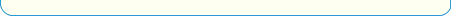
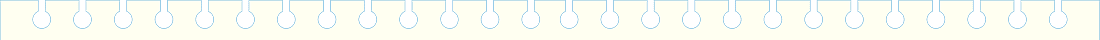
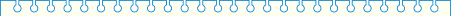
保育環境をつくる
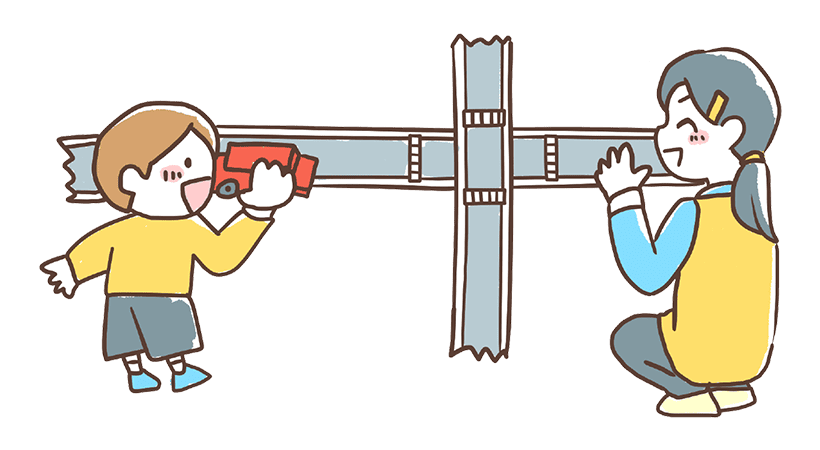
子どもの発想を活かして
車を壁に走らせて遊んでいる子どもがいました。そこで、道路のイラストがデザインされているマスキングテープを壁に貼ってみると、大人気のコースとなりました。
遊びの環境は、子どもたちの姿に合わせて設定していきます。
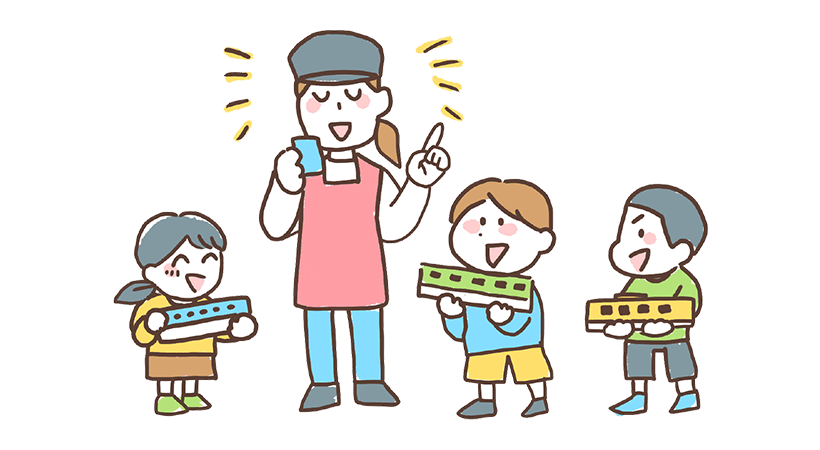
遊びを豊かに
電車が好きな子どもが新幹線の玩具を手に「先生、一緒に1番線に行こうよ」と誘ってくれました。子どもの後ろをついていき、「1番線に新大阪行きのぞみがとまります」と駅のアナウンスをすると子どもは大喜び。ほかの子も電車をもって合流していました。
大人も一緒に遊ぶことで、遊びの世界が広がるきっかけ作りを大切にしています。

鉄棒をもっと
楽しんでもらうために
鉄棒をより楽しんでもらうため、様々な鉄棒技のイラストをまとめたカードを作成しました。できた技にはシールを貼ることで達成感を感じ、次の技に挑戦する意欲につながっていました。
子どもたちの意欲を引き出せるよう、工夫しています。

一人ひとりに合った
環境作りを目指して
その子にとって今必要な援助とは何か、互いの視点や考えを尊重しながら意見交換し、園全体で協力し合える園作りを大切にしています。
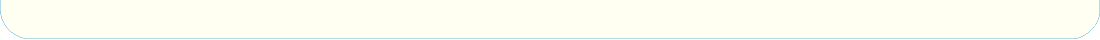
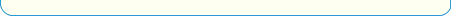
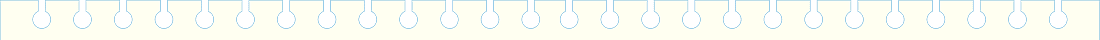
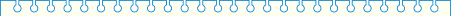
子ども一人ひとりの意思を尊重し、 自主性や主体性を持った意欲溢れるこどもを育てる 子ども一人ひとりの 意思を尊重し、 自主性や主体性を持った 意欲溢れるこどもを育てる
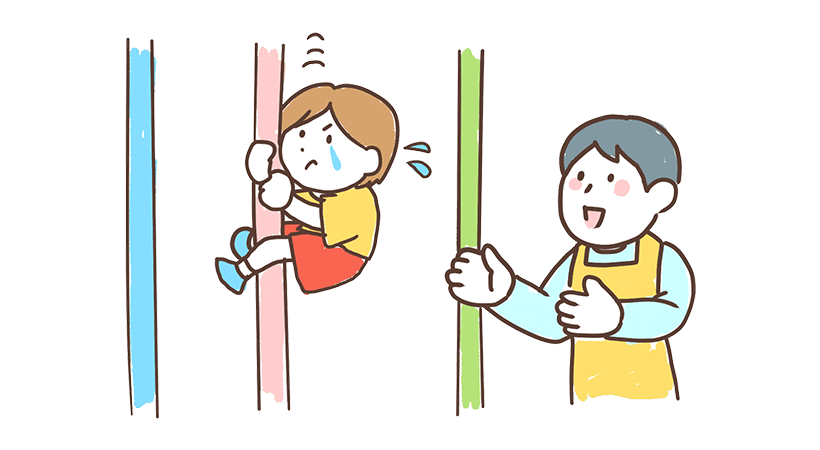
子どもが考えて
選択できる機会を作る
上り棒の途中で怖くて止まっている子どもがいました。目を合わせて、いつでも手伝えることを表情で伝えると、少し考えてから、再び上り始めました。いつでも挑戦できるし、いつでも頼れる大人がいる。その選択は子ども自身ができるようにしています。
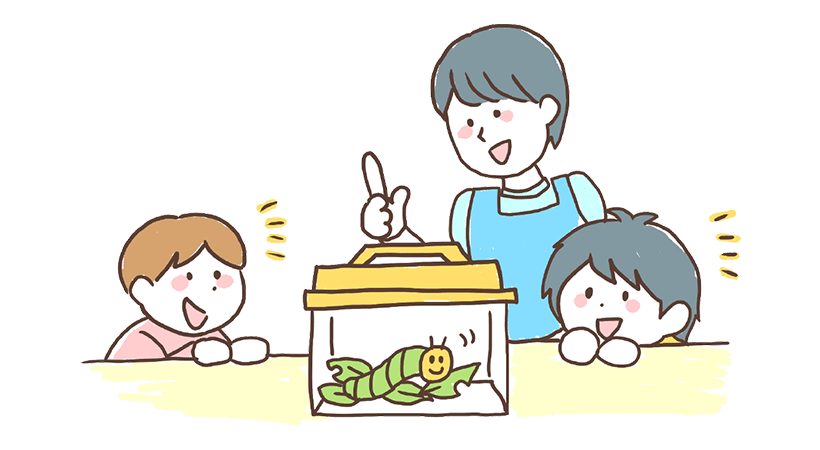
興味の輪を少しずつ広げる
公園で見つけたアオムシ。「育ててみたい」と子どもたちから声があがったので、園に持ち帰りました。興味のある子どもだけでお世話を始めましたが、アオムシの成長の様子を掲示したり、図鑑を用意していると日に日に他の子にも興味が広がり、アゲハ蝶となって外へ逃がすときには多くの子どもたちが「がんばれー!」と飛んでいく姿を見送っていました。
子ども自身が様々なことに気づき、興味関心が広がっていくように工夫しています。
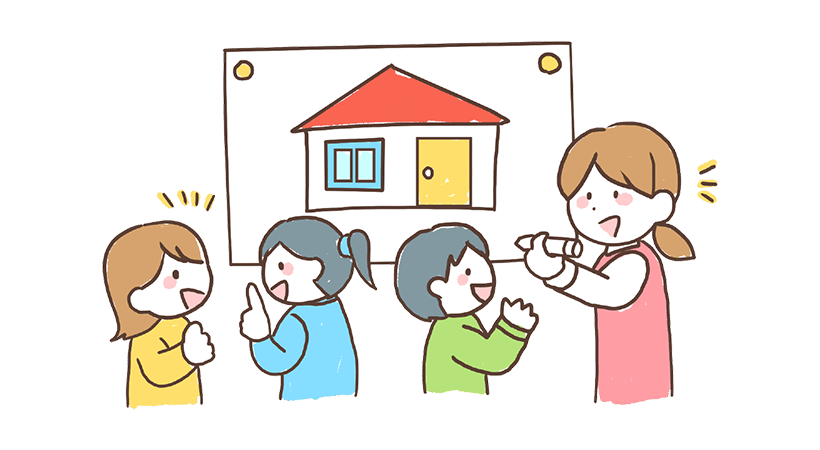
子どもが進めていく
過程を大切に
行事も、何をやりたいか子どもたちが話し合い、必要に応じて大人が問いかけながら、進めていきます。運動、制作、自分がやりたいこと、みんなとやりたいこと、保護者と一緒にやりたいこと、その過程の中でうまくいかない葛藤や経験を大切にしています。
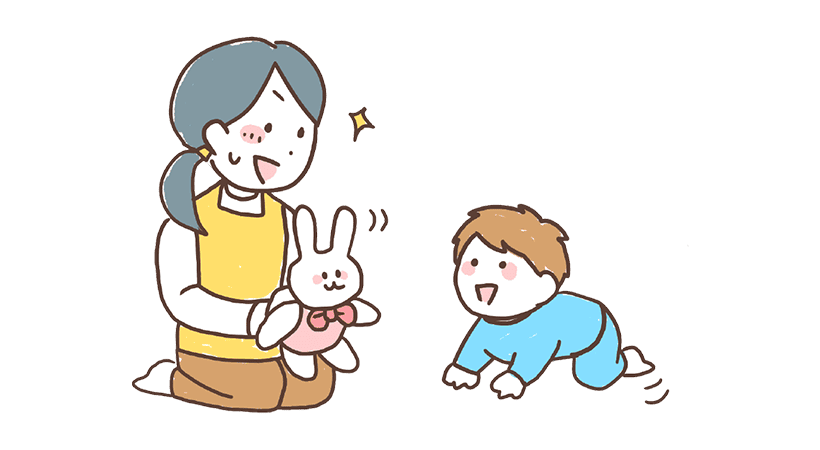
思いを汲み取る
子どもの願いや思いは何か、その言葉の本当の思いはどこか、子どもの姿や背景から汲み取ることを大切にしています。色々な視点からその子を知っていき、必要な援助は何かを話し合って環境を整えています。
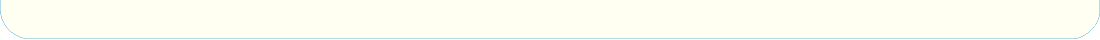
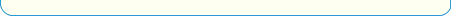
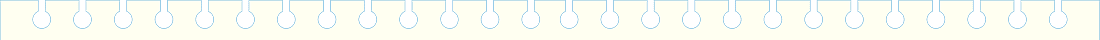
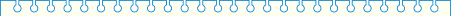
1人ひとりの育つ力に働きかけ、
信じて待つことで花開かせる保育
1人ひとりの
育つ力に働きかけ、
信じて待つことで
花開かせる保育

一人ひとりの
タイミングを大切に
泥が苦手なお子さんがいました。その子が好きなもので遊べる環境を整えながら、楽しく遊ぶ姿を見せ、気になっている姿があったらさりげなく触れられるようにしているうちに、自ら足に泥をつけて遊び始めました。その子のタイミングを奪わないこと、逃さないことを大切にしています。
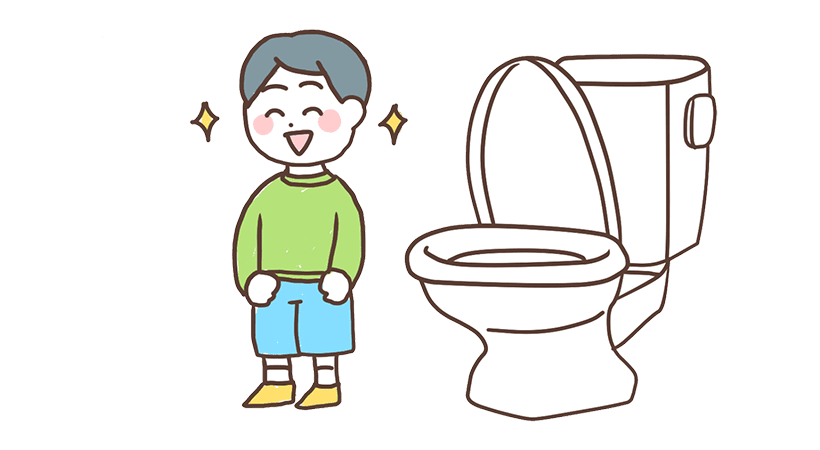
一人ひとりのタイミングで
排泄の自立は、身体の機能と心の準備ができてからだと考えています。無理に自立させるのではなく、お子さんの様子に合わせて、ご家庭と協力しながら援助しています。
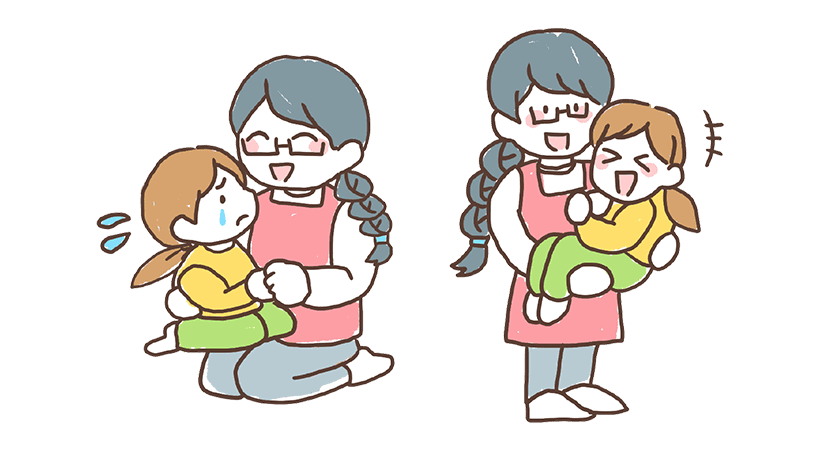
甘えたい気持ちを
とことん受け止める
甘えたいとき、悲しい時にはその時その子の気持ちを十分に受けとめ、自らの意思で次へ向かえるように援助することを大切にしています。
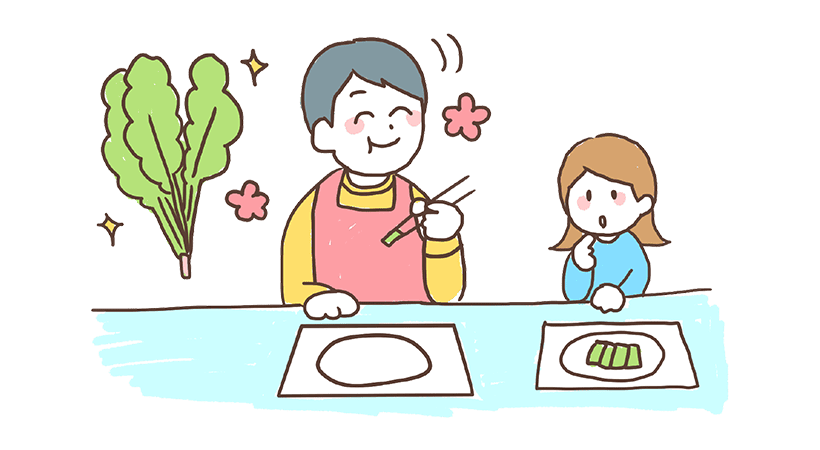
食事は大好きな人と
楽しく過ごす時間
「夏に育つ野菜があるんだけど、知ってる?」と保育士が問いかけ、育てたい野菜を子どもたちと考えました。苦手なものを無理強いするのではなく、栽培やクッキング、食育を通して「食べてみよう。」と思える取り組み、環境を考えています。